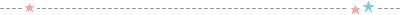novel
□素敵なディナー
1ページ/1ページ
それは、ある金曜日の夜の事。
蔵馬は忙しい仕事を終え、足早に家へと急いでいた。
家ではぼたんが待っていてくれる。
その顔を思い出すだけで、自然と歩く足も軽快になった。
いつもよりも遠く感じた自宅。
やっとの思いで辿り着いた家に一歩入ると、安堵からなのか、一週間の疲れがどっと押し寄せて来たような気がした。
「おかえり!蔵馬!」
とびっきりの笑顔が出迎えてくれる。
その顔をみただけで、蔵馬はその疲れも忘れるようだった。
「ただいま、ぼたん。」
疲れた身体で仕事から帰宅したが、ぼたんが沸かしてくれた風呂にゆっくりと浸かると、心も身体も満たされて行くのがわかった。
「はぁーーー。」
蔵馬は、柄にもなく、深い深いため息をついた。
もちろん、至福のため息だった。
身体を温め、頭の中を空っぽにしていると、何だかいい匂いがして来た事に気が付いた。
食欲をそそるような、そして、いかにも幸せを漂わせるような、家庭的な、おいしそうな匂いだった。
その頃キッチンでは、蔵馬に言われ、先に風呂を済ませると、せっせと夕食の支度をしているぼたんがいた。
蔵馬は、そんなぼたんの様子を想像しながら、「今日の晩御飯は何だろう」と、その匂いに浸った。
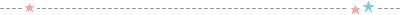
「うっ・・くっ・・」
(何だ・・?)
蔵馬が風呂から上がると、キッチンから奇妙な声が聞こえてきた。
不思議に思った蔵馬は、その声の方へゆっくりと近づくと、気付かれないように、そっと様子を窺った。
「くっ・・。だ・・ダメだ・・。ビクともしないじゃないか。何でこんなに固くしまってるんだい。」
そこには、何かの瓶のふたを必死で開けようとしているぼたんの姿があった。
料理で使いたいのか、顔を真っ赤にさせて、力を振り絞っていた。
風呂上がりでほのかな石鹸の香りを漂わせながら、トレードマークのポニーテールを下ろし、艶やかになびかせながらも、その反面、顔を赤くして必死になっているぼたん。
一緒に住むようになって初めて見られる姿の数々が、蔵馬には、とても大切なものだった。
さらに、それが自分だけが見られる特権だと思うと、優越感と独占欲が生まれた。
ぼたんの色んな表情を見たくて、気が付けば、助ける事も忘れて、思わず見とれていた。
蔵馬は慌てて、ぼたんの元に行くと、何も言わずに瓶をひょいっと取り上げ、何でもないように簡単に蓋を開けて、ぼたんに返した。
「蔵馬!」
蔵馬が風呂から出ていた事に気が付いていなかったぼたんは、戻って来た瓶と蔵馬を見て、すぐに顔が綻んだ。
「さっすがは蔵馬!あたしじゃ全然開かなかったっていうのにさ。簡単に開けちゃうんだから。」
ぼたんは目をキラキラさせて喜んだ。
蔵馬は、ぼたんの笑顔に思わず微笑んだが、すぐに視線をその先に向けた。
「何、作ってるんです?」
蔵馬はそう言って、クツクツ音のしている鍋を覗こうとした。
その蔵馬の前に、ぼたんは慌てて立ちはだかった。
「な、内緒!!」
「何で、内緒なの?」
ぼたんの俊敏な動きに、蔵馬は思わず笑って言った。
「いいからっ!」
「だって、俺も食べるのに?何で隠すんですか?」
「別にいいだろ。」
「何か、理由があるんですか?」
「・・・・なの」
「え?なんです?」
「お・・お楽しみなのっ」
ぼたんはせっかく赤みが退いた顔を再び赤くして、小さな声で恥ずかしそうに言った。
蔵馬は、それを見ると、抑えきれない感情が込み上げ、思わずぼたんを抱きしめた。
(本当に、あなたは・・。どうしてそんなに可愛いんですか)
蔵馬には、自分の為に一生懸命になっているぼたんが、可愛くて愛おしくて仕方がなかった。
「な、何だい。蔵馬。もう。あっち行っとくれよ。」
ぼたんは恥ずかしそうに言った。
「・・やっぱり、お楽しみですか?」
蔵馬はぼたんを抱きしめたまま、ぼたんの顔も見ずに、少しいじけたような声で言った。
「もう。まだ言ってんのかい?」
「少し味見させてください。」
「ダメだって言ってるだろ?我慢出来ないのかい?」
「あまりにも美味しそうな匂いがしたので、早く食べたくなってしまったんですよ。」
蔵馬は、愛おしそうに、ぼたんを抱きしめる手にぎゅっと力を込めると、そう耳元で囁いた。
「あんたって、そんなに食いしん坊だったかい?」
蔵馬の言動に、ぼたんは堪らずケラケラと笑った。
「明日は休みなんだからさ。そんなに焦らなくてもいいじゃないか。ちゃんと味わっとくれよ。」
ぼたんはそう言って、蔵馬の腕を解くと、料理に取り掛かろうとした。
「すぐ出来るから、待ってておくれよ!」
蔵馬は、自分の腕から解放されたぼたんを見ると、クスクスと笑った。
「そうじゃなくて。あなたの事ですよ、ぼたん。」
そう言って、蔵馬は、ぼたんの首筋をぺろっと舐めた。
「!!えっ・・なっ、ちょっと・・!」
ぼたんは驚いて、すぐさま自分の首を手で抑えた。
風呂上がりのぼたんの優しい香りが、蔵馬の鼻腔を刺激する。
その甘い誘惑が、蔵馬の感性も理性も、コントロール出来なくさせる。
「本当に、美味しそうだな・・。」
蔵馬は、ぼたんの髪に顔を擦り寄せ、その香りを味わった。
感覚や、脳さえも麻痺させるようなその妖艶さに、一瞬自分が妖孤に戻っているのではないかとさえ思わせた。
「蔵・・馬・・。」
ぼたんは、ピクッと少し反応すると、そのままどうしていいかわからずに、蔵馬にされるがままになっていた。
蔵馬は、身体を強張らせて動けなくなっているぼたんに気が付くと、その腕を優しく掴み、ゆっくりと少し身体を離した。
「そうですね。明日は休みですし・・。」
「ゆっくり頂く事にします。」
蔵馬は、にっこりと笑って言った。
「なっなっ・・」
ぼたんは顔を真っ赤にして、口をパクパクさせた。
「おっと。あなたの要望も、もちろん聞きますよ。安心してください。”ちゃんと、味わいます”から。」
「あたしはっ・・そんなつもりで言ったんじゃ・・!!」
蔵馬は楽しそうにしながら、ぼたんの言葉を聞かずに、キッチンを後にした。
あなたが、必死に抵抗すればするほど、俺には逆効果なんですよ。
ぼたん。
今日は 素敵なディナーに なりそうです。
蔵馬は食卓に就くと、真っ赤なバラを2本飾り、それを満足そうに眺めた。
-end-
■あとがき■
読んでくださった皆様、ありがとうございました!
今回は、ちょっと甘めのお話です。
でも、やっぱり、どうしても蔵馬が攻めてしまってます(笑)
今回もDiaryに、この話を書いたきっかけなど、あとがきを載せておりますので、宜しければそちらも合わせてご覧ください(^^)