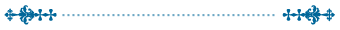青風と七武海
□03
1ページ/1ページ
ユウを連れて親父に報告に行くとただ、そうか娘か、と言い嬉しそうに笑った。
「え、娘なんですか?」
親父の部屋を出てからすぐユウが聞いた。
「娘ってのは別に白ひげ海賊団になったと思われたわけじゃねぇよい。一度船に乗ったらみんな家族だ。」
へーっと不思議そうな、でも決して嫌そうじゃない顔で頷いていた。
マルコはユウを見下ろす度に感じる既視感を持て余していた。
「あ、サッチさんだ。」
「ユウちゃん親父んとこ行ってきたか?」
「はい、思っていたより優しい方でした。」
サッチの顔が若干デレっとして気持ち悪いのは仕方がない。
そんな顔を見せるのは彼だけではないのだから。
「おい、お姫さんこっち来な。」
甲板の端からイゾウが声をかけてきた。
「あ、イゾウさん…。」
ユウが顔を赤くさせながら走っていく。
「イゾウ、ユウのこと構いすぎだろ。面白いことになってんな。」
サッチも暇だからとイゾウの方へと近づいていった。
マルコは部屋に帰ろうかと思ったが樽に座ったイゾウがユウの手を取っているのを見て衝動的にサッチの後を追ってしまった。
「お前さんの獲物見せてみな。」
イゾウはユウを自分の隣に座るように促しながら言った。
「あ、はい、これです。」
ユウが腰に巻いているベルトからリボルバーを3丁引っこ抜く。
「特に何の変哲もないリボルバーですよ。」
「ライフルとかじゃダメなのかよい。」
「これは部品が少ないので手入れしやすく、不発があってもすぐに次弾を撃てるんです。リボルバーは標的に命中させるのもさほど難しくなくて初心者向けだったんですよ。」
"初心者向けだった"という言葉はリボルバーを選んで訓練する彼女の"始まり"があったことを意識させた。
「なぁ、ユウちゃんはどうしてそんな生活してんだ?普通の女の子にしか見えねーのに。」
サッチもマルコと同じことを感じたようだ。
「長くなりますよ。」
そう言ってユウは微笑んだ。
「私が5歳の頃でした。友達と遊んでいる間に海賊が村を攻めてきて、私の家は焼かれたんです。」
イゾウの眉が苛立たしげに顰められた。
「それを聞いて慌てて家に走って帰ったんですけど、両親は崩れて燃え上がる家の下敷きになっていました。」
突然、マルコは緑の大地に炎をあげる真っ赤な家を思い出した。
海賊になってから嫌というほど見てきた似たような光景とは違う、それは確かな一つの記憶だった。
無意識にあっと叫びそうになった声を喉の奥に押し込んだ。
「変わり果てた家を見て呆然と泣きじゃくる私に誰かが叫んだんです。」
記憶の中の自分は燃え盛る家を前に号泣する小さな少女を見つけた。
少女の顔は絶望を映し出している。
マルコは叫んだ。
「"生きろよ"って。」
「私にそう叫んだ男の人が海賊から村を救ってくれたと聞きました。村の人たちはとても優しくて、私はみんなから愛されて特に不自由することなく育つことが出来ました。でもダメだったんです。」
ユウがサッチに向かって自虐的に微笑んでみせた。
「私、どうしてもその海賊が許せなくて。村の人たちは復讐なんてしちゃダメだってその海賊のこと教えてくれなかったんですけど、同じような海賊はたくさんいます。それを思うと生まれ育った島でのんびり生きることが出来なくて。海に出ました。」
仕方ない奴ですよとユウは笑った。
「お前…今までよく生きてこれたな。」
サッチがユウの髪を撫でた。
「ピンチの時はいつも聞こえたんです。あの時叫ばれた"生きろ"っていう声が。それが誰なのか、姿さえも覚えていないんですけど、何かあった時はその声に生かされてきた気がします。」
そう言って笑ったユウの笑顔はとても綺麗でマルコはドキッとした。
「それなら、そう言ったやつも本望だろうよい。」
心の底からそう言えばユウは嬉しそうに頷いた。
「今ごろお前さんの手配書でも見て笑ってやがるかもなぁ。」
「そいつ今も生きてたらいいな!」
マルコはさすがに苦笑してしまった。
いつの間にか人気者になってしまったユウがナースにお茶会へと引っ張っていかれた後、マルコは部屋に帰ろうとしたところをサッチに呼び止められた。
「そんでお前、ユウちゃんのヒーローに心当たりでもあんじゃねーの?」
「…何言ってんだよい。」
サッチはたまに驚く様な鋭さを発揮する。
しかもいらないときに限ってだ。
「ユウちゃんが飛んできてからお前たまにおかしいぜ?おれはお前のことよく見てっからな。」
「気持ち悪いこと言うんじゃねーよい!」
「怒んなって。まさかお前がヒーローか?」
何も言わずにいたら沈黙を肯定と受け取ったようだ。
「マジかよ。おい、言わねーのか?」
「言うわけねーよい。」
「イゾウに取られたくないんじゃねーの?」
「…ユウは忘れている。俺が言ったところで思い出さないだろうねい。」
いきなり自分があの時の男だ何て言ってもユウは心から信じることが出来ないだろう。
もし安易に言ってしまい、釈然としないままそれをユウが受け入れてしまうのは怖い。
ちゃんと真実を思い出して欲しかった。
「そっか。まぁ頑張れよ。」
サッチはそういうと飯の用意だと食堂へ消えていった。
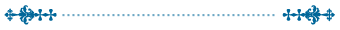
サッチの口調が分からなくなってきました。
.